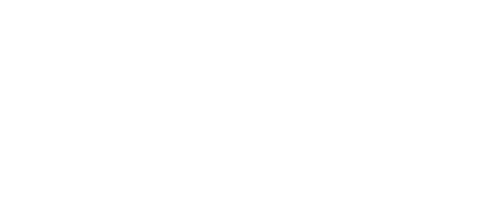30年越しの悲願を実現する岐阜県土岐工場の開所
 小日向: このたび開所される「土岐工場(岐阜県)」の概要、および期待されることについてお聞かせください。
小日向: このたび開所される「土岐工場(岐阜県)」の概要、および期待されることについてお聞かせください。
長谷川: 航空機メーカーより、従来機から新型機への移行過程での増産に対して協力依頼がありました。担当工場の滋賀工場では全く拡張の余地がなく、これ以上の設備増強のためには工場用地を確保しなければなりません。そのような経緯があり、客先に近く航空産業の一大市場である中部地区への進出を決めました。実は中部地区進出は30年越しの悲願であり、さまざまな条件が整い、今日を迎えることができました。
土岐工場の特徴は、省力化、省人化をテーマに合理化に根差した工場づくりを目指していることです。当然のことながらグローバル市場を意識した展開も視野に入れています。
小日向: 土岐工場の開所目的は、航空・宇宙産業向けということですね。アルバックの熱処理炉は、今まで自動車関連用途が多かったのですが、航空機業界向けにも伸ばしていきたいと思っています。今後、航空機業界向け真空熱処理炉に求められるのはどのようなことでしょうか。
長谷川: アルバックさんの真空熱処理炉の特徴として、生産性の高い多室式真空熱処理炉が挙げられますが、従来の真空熱処理炉では実体温度測定が困難であるように認識しています。
航空分野では実体温度測定を行うことが品質保証の一部として謳われている場合がありますので、処理品が処理室間を移動しながらも実体温度測定可能な方法とか仕組みが必要です。先日アルバックさんより画期的な提案をいただきました。これを航空対応に発展させて認証機関の承認が取れれば、大きな可能性が広がると思います。楽しみにしています。これが完成すれば革命ですよ。
常に体質に変化を!甘えは身を滅ぼす
小日向: 多室式真空熱処理炉で実体温度測定ができたら革命ですよと、大変嬉しいお言葉をいただきました。さて御社は、経営方針に「つねに変化を先取りし、多くのソリューションを提供し、たゆまず技術革新に挑戦し、さらにポテンシャルを高めていきます」と掲げられ、創業から受け継がれた精神を根幹に、将来を見据えた開発をおこなっていらっしゃいます。ノウハウの蓄積と新たなプロセス開発を行うための体制やその工夫をお聞かせください。
長谷川: 先代から受け継いだところとして、設備投資は積極的におこなっておりますが、決して「設備ありき」ではありません。目的があり将来の「メシの種」に必要であれば、独自の仕様や改良を加えた形で先行的に導入します。
齋藤: 将来「メシの種」になるのなら先行的に導入するとおっしゃられましたが、「メシの種」になる判断は難しいことです。まさにHIPの焼結がそうですが、その判断基準にされているのはどのような点でしょうか。
長谷川: 当初HIPを導入する引き金は液晶市場でしたが、到達点は航空機、つまりジェットエンジンのタービンケースやコンプレッサーのためのものでした。今はエンジンが小型化・軽量化され、ターゲットは変わってきていますが手一杯の状況です。
いずれにしても設備はどのように使うかが重要です。我々中小企業の優位性は、取り組みの早さや小回りのきく点だと思います。現在進んでいるグローバル化によって、企業の大小の垣根がなくなり、古きよき時代の大企業然とした、外部委託先の面倒をみるような風潮は全く無くなってきています。何とも厳しい時代ですね。
ですから、身軽な決裁の早い中小企業は常に先行し、追いつかれた時には、また次のステップに行っていなければ食われてしまう。決して大企業の批判をしているわけではありません。それだけ厳しい世の中になったということ、そして、中小企業も体質を変えていかなければならないということです。甘えは身を滅ぼすことになるように思います。
小日向: HIPはかなり大きな投資だったようですね。
長谷川: HIPのときは反対が多かったですね。私の決裁で思い切って断行しました。全体で60億円の投資でしたが、少し大げさに言いますと、これは当時の年間売上げに迫る額です。
小日向: これは凄い。弊社なんか売上高の10%の金額でビビっているくらいですから。(笑)
長谷川社長の持論で「苦労すれば、苦労するほど成果が大きい」ということをおっしゃられていますが、全く同感です。私は「開発は、やった分だけ利益が後からついてくる」、開発を惜しんでいるような会社は伸びないし、利益も生まない。まずお金を使わないといけませんね。御社では開発はどのようにされていますか。
長谷川: この辺は中小企業の泣きどころといえましょうか、先の見えないものになかなか大きな予算を設けられないのが実情でした。過去から開発本部なるものを設けて活動した時期がありましたが、工場と直結していないことと、生産技術色が強くなり、工場の生産技術部門とオーバーラップしたりして、なかなか思うような成果が上げられませんでした。
現在は技術本部を設けて活動しておりますが、工場のスタッフもメンバーに加え、市場、お客様のニーズならびに将来の動向など工場や営業の情報をもとに、プロジェクトスタイルで技術の定着と研究開発の両面で進めております。