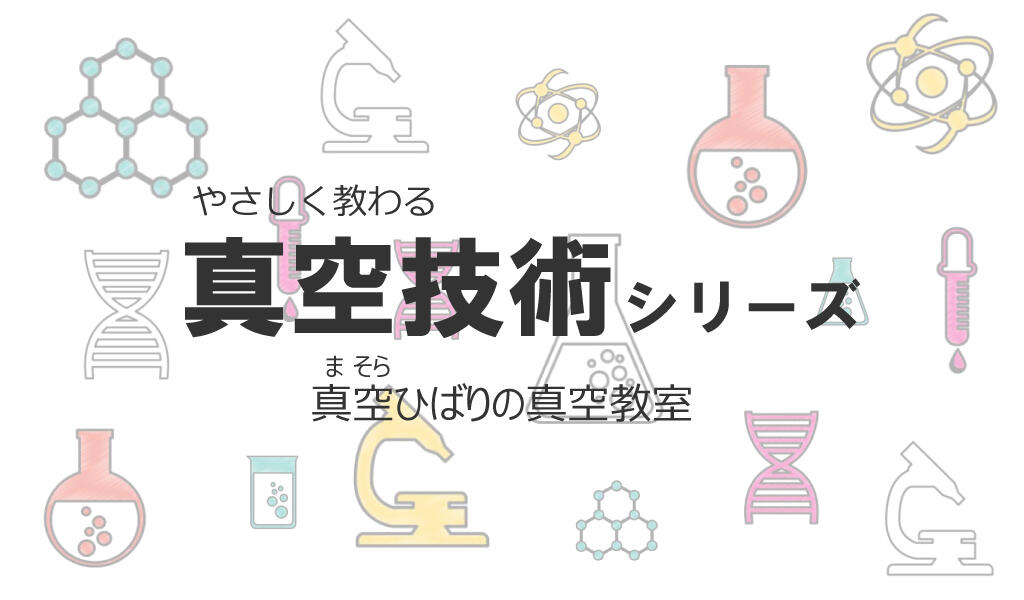システムインパッケージ(SiP)とは複数の半導体チップを1つのパッケージ内に封止する技術ことです。半導体Chipをそれぞれ作製し、実装プロセスで組み合わせます。
対してシステムオンパッケージ(SoC)は1つの半導体チップ上に異なる機能を集積する技術です。例えば、CPUと大容量メモリ、高耐圧電源ICと低電圧CPU、などをワンチップ化する技術のことをいいます。
SiPは、チップ間の配線を設けるため、SoCと比較して応答速度などで性能が低いこと。SoCは、高い歩留まりをKeepするのが困難であることと、製造工期が長いなどそれぞれ違いがあります。
再配線層、Build up配線以外にも、SiP向けにプラズマ技術は応用されています。 この動画ではULVACが提供する表面改質処理といったアプリケーションを紹介します。
アッシング装置紹介はこちら
実装工程プロセスの紹介はこちら
お問い合わせはこちら

Printed Circuit Board (PCB)とは絶縁体の内部、または、表面に金属配線が施された電子部品が取り付けらる基板のことです。半導体パッケージ(実装)製品の王道製品と言えます。 アルバックは、PCB製品の微細化技術に一役買っています。 将来をターゲットに据えたドライ化技術について紹介します。
アッシング装置紹介はこちら
実装工程プロセスの紹介はこちら
お問い合わせはこちら

最先端のパッケージ(実装)製品には、プラズマ技術が既に使われています。アルバックではウェハー、パネル向けのプラズマアッシング装置を提供しています。これらのアッシング装置はバッチ式ではなくアッシングレートの面内分布を意識した枚葉式の装置です。
一般的にアッシングとは、フォトレジストをプラズマで分解し除去する工程です。アルバックでは実装の工程のアッシングは比較的簡単なエッチングをするという意味合いで使われています。
アッシング装置紹介はこちら
実装工程プロセスの紹介はこちら
お問い合わせはこちら

半導体パッケージ(実装)製品のトレンドと言えば、ファンアウト(Fan-out)。アルバックはファンアウトパッケージの量産化技術に貢献しています。 ここでは、プロセスフローとプラズマ技術についてご紹介します。
Key word
Fan-Out(FO) : チップに対して扇状に配線を広げた構造。
Package on Package (PoP) : パッケージを積層した構造。
Redistributed layer (RDL)、再配線層 : チップと外部取り出し部までの配線層
Descum : フォトリソグラフィー後の残渣を除去する工程
感光性樹脂 : 光を照射することで性質が変化する高分子材料の総称。
Polyimide : Imide結合を含む高分子化合物の総称。
アッシング装置紹介はこちら
実装工程プロセスの紹介はこちら
お問い合わせはこちら

プラズマ発生方法は、沢山種類があります。その中で、アルバックはパッケージ(実装)製品に適したプラズマ源を採用しています。主に下記の放電方式があります。
Surface Wave Plasma (SWP) : マイクロ波の表面波によって誘電体透過窓表面に表面波を生成。この表面波によって、透過窓付近にプラズマを発生する方法。
Capacitively Coupled Plasma (CCP) : 2枚の金属電極に片方に高周波電源が接続されており、 極板間の電場形成によってプラズマを発生する方法。
Dual frequency Capacitively Couple Plasma (2-Freq CCP) :2枚の電極基板それぞれに異なる高周波電源が接続されているCCP方式。
アッシング装置紹介はこちら
実装工程プロセスの紹介はこちら
お問い合わせはこちら

半導体チップの微細化が難しくなっている中、デバイスの性能を高めるためにパッケージ技術が注目を集めています。異種デバイスを集積し、高性能化する技術を「More than Moore」といい複数の半導体パッケージを一つの半導体パッケージに封止する技術をシステムインパッケージといいます。
アルバックは半導体パッケージ(実装)の量産化技術の開発に力を入れています。ここでは、パッケージ(実装)向けプラズマ技術の背景をご紹介します。
アッシング装置紹介はこちら
実装工程プロセスの紹介はこちら
お問い合わせはこちら
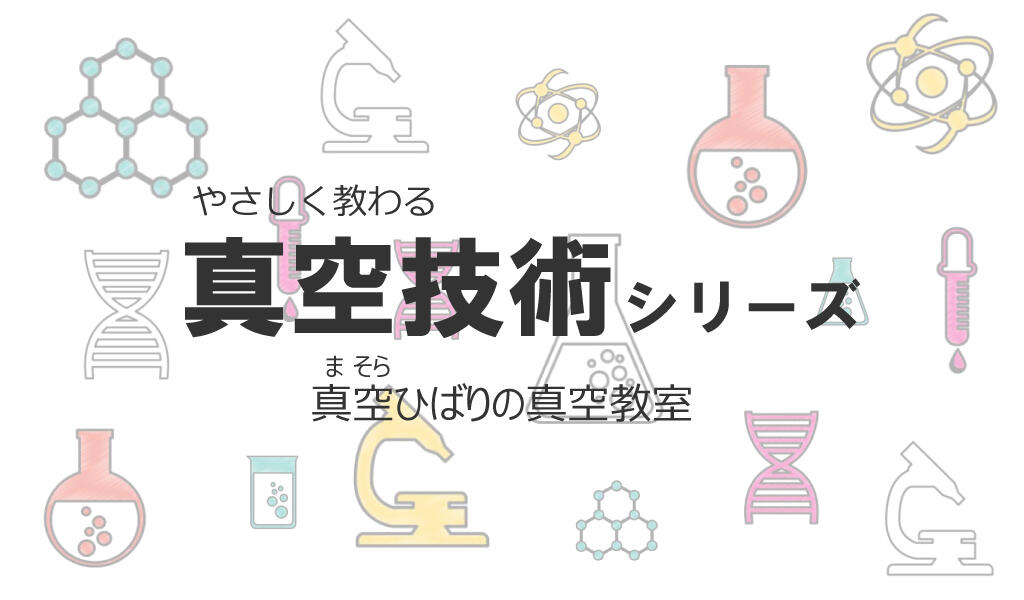
真空ひばりの真空教室 Vol.24
はじめまして! 真空(まそら)ひばりです。この教室で皆さんに「真空」のことをいろいろレクチャーしていきます。よろしくネ♪
物質の表面分析は真空中でこそ可能となる
これまで、いろいろな製品やデバイスがどのように真空を利用してつくられているのかをお話してきましたが、この教室の最後に、真空を応用して物質の固体表面を分析する方法について、お話したいと思います。低速荷電粒子(電子イオン)を分析に用いると、固体の表面だけの情報を得ることができます。たとえば、固体試料を真空中に置いてイオンをぶつけると、最表面の原子・分子が真空中に飛び出します。そう、スパッタリング現象です。
こうして表面から出てきた原子や分子の一部はイオン化していて、このイオンの質量と数を計測することによって、固体表面の原子・分子構成を知ることができるんです。この手法は、SIMS(二次イオン質量分析法)と呼ばれ、半導体産業を始めとする多くの産業分野で用いられています。
表面に刺激を与えて飛び出した電子のエネルギーを計測
表面分析は、表面の原子・分子に与える刺激(プローブ)と、計測する荷電粒子の組み合わせによって、何十種類もの手法があります。表面分析法としてはSIMSのほかに、X線を照射して出てきた電子の運動エネルギーを計測する手法(X線電子分光法 : XPSまたはESCA)や電子を照射して出てきた電子の運動エネルギーを計測する手法(オージェ電子分光法: AES)などが一般的によく使われています。
AESは、試料に電子を当てることで出てくる電子を分析するものです。原子核のまわりの電子に電子を当てて空席にすると、外側の軌道を回る電子がそこに落ちて、そのときにX線を出さずに、そのエネルギーによって電子が飛び出すことがあるため、その飛び出した電子を分析することで元素の種類が特定できるんです。そして電子の代わりにX線を当てて、出てきた電子の運動エネルギーを計測するのがXPSです。
表面分析法は、とても多くの産業・科学研究分野において、新しい特性や機能を備えた物質の研究開発・品質管理に欠くことのできない手法として、長い間ずっと進歩を続けてきましたし、これからも必要不可欠なものなんです。
以上で私の「真空教室」はひとまず終わりです。長い間、私の拙い講義にお付き合いいただき、ありがとうございました。
用語解説原子物質の基本的な構成要素で、原子核と電子とから構成されています。自然に存在する物質は92種類の原子からなりますが、人工的につくられる寿命の短い原子十数種類の存在が確認されている。
アルバックホームページ
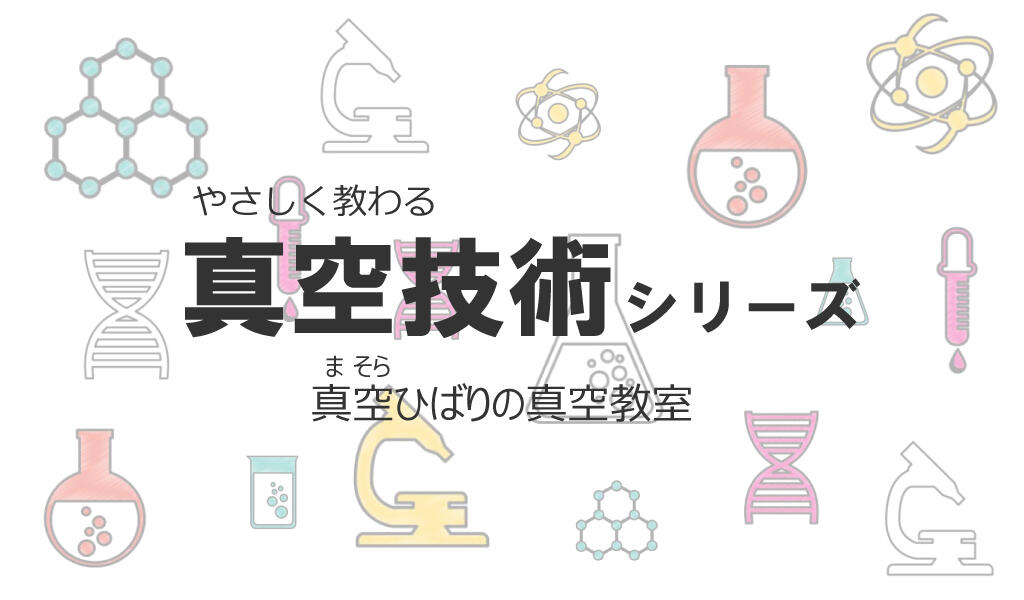
真空ひばりの真空教室 Vol.23
はじめまして! 真空(まそら)ひばりです。この教室で皆さんに「真空」のことをいろいろレクチャーしていきます。よろしくネ♪
魚釣りで使う道具「ルアー」も真空内の蒸着重合を応用してつくられている
「えっ、こんなものも真空と関わりがあるの?」と思ってしまうくらい、意外なものに真空技術が使われている、というのが今回のお話です。いろんなアウトドアスポーツの中で、魚釣りを楽しむ人もたくさんいますが、気軽にできて人気が高いのがルアー釣りです。ルアーは疑似餌のことで、魚に似せた形の金属にめっきや塗装を施したものが使われています。
ルアーにライン(釣り糸)を結んで投げて、リールでラインを巻き取ると、ルアーは水圧を受けてさまざまな動きをします。ただの金属片やプラスチック製のルアーが、まるで小魚のように泳いだりきらめいたりするため、これを見た魚が餌だと思ったり、敵だと錯覚したりして反射的に食いついてしまうんですって。古くから親しまれてきたこのルアーで、成膜法を応用した製品があります。表面に「蒸着重合」という方法で皮膜をつけるもので、角度によって色合いが変化するホログラムカラーが魚の気を引くようです。
基板上でモノマーを重合させる蒸着重合
蒸着重合とは、真空中で2種類のモノマーを同時に加熱して蒸発させ、基板上で重合反応をさせてから、高分子ポリマー膜として成膜する方法です。ルアーでは、無水ピロメリト酸オキシジアニリンの2つの原料モノマーを使いますが、従来の方法ではこれらをまず、重合反応させてポリマーにしてから基板に塗布していました。これに対して蒸着重合法は、真空内で別々に蒸発させた基板表面で重合反応を起こさせるため、薄膜の生成が可能となりました。その結果、ポリイミドやポリアミド、ポリ尿素などの樹脂を数nmから100μmまでの範囲で成膜できます。
蒸着重合法は、1984年に新しい機能性高分子成膜法として開発されました。成膜された高分子膜は、絶縁膜・断熱膜・保護膜などの機能性膜として利用され、すでにセンサやモーターコア、医療機器への応用が実用化されています。
ルアーへは、成膜面のもつグラディエーション性とホログラフィー性から応用されたもので、真空技術は最先端のデバイス製造だけでなく、こうした日用スポーツ品へも広がりを見せているんですね。
用語解説モノマー/ポリマー
同じ種類の小さな分子が互いに多数結合して巨大な高分子となるとき、小さい分子をモノマー(単量体)、生成した高分子をポリマー(重合体)という。
アルバックホームページ
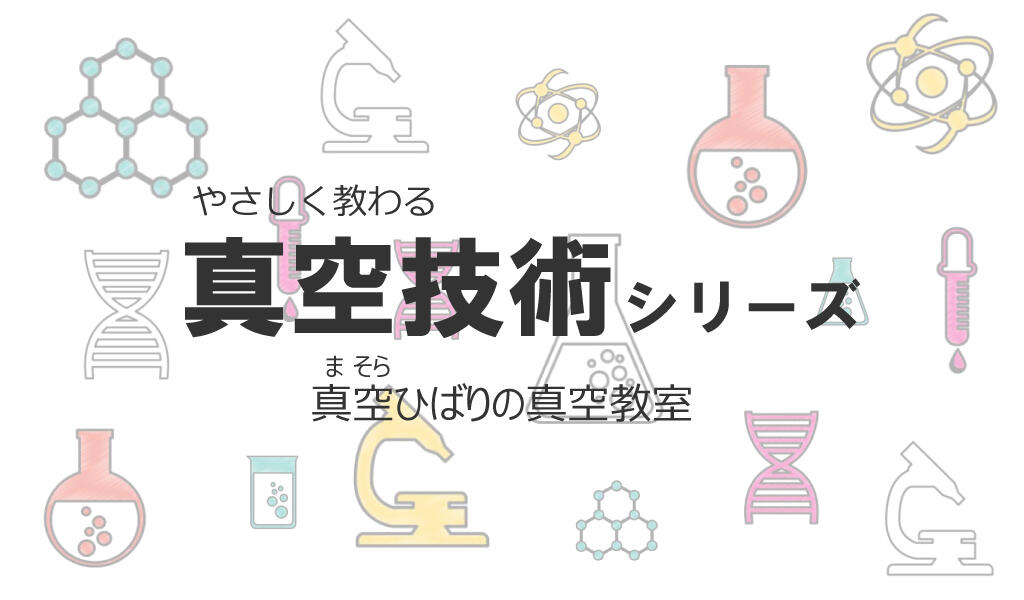
真空ひばりの真空教室 Vol.22
はじめまして! 真空(まそら)ひばりです。この教室で皆さんに「真空」のことをいろいろレクチャーしていきます。よろしくネ♪
ひげ剃りの刃の表面コーティングにも利用されている真空内での硬質皮膜処理
真空技術に支えられているものがたくさんあることは、これまでのお話で理解してもらえていると思いますが、今回は真空内での硬質皮膜処理のお話です。ホームセンターの工具売り場で売っているドリルなどの切削工具の中で、刃の部分に金色のコーティングが施されているものを見たことはありますか?このドリルの刃には、表面にTiN(窒化チタン)などの硬質皮膜が数ミクロンの厚さでコーティングされています。TiN膜は、硬くて耐摩擦性に優れた薄膜で、金属との密着性もよく、切削工具表面処理コーティングには適しています。
この硬質皮膜が施された工具は、無処理の工具に比べて寿命が数倍長くなるという特徴をもっているんです。硬質皮膜としては、TiNの他にもTiC(炭化チタン)、TiAIN(窒化チタンアルミ)などがあって、それぞれ硬度、摩擦係数、耐熱性の違いに応じて金型、自動車用部品、いろいろな装飾品などの表面処理コーティングに使われています。
そしてこれらの硬質皮膜の成膜には、イオンメッキとも呼ばれるイオンプレーティングによるものが多く用いられていますが、その他には、スパッタリング、CVD法などの手法も使ってコーティングされています。
ダイヤモンドのように堅いDLC(ダイヤモンドライクカーボン)
もう一つ別のコーティングのお話をします。私はもちろん使うことはないけど、ひげ剃りの刃は、切れ味を良くするために、すごく薄くなっていますが、薄くなった分の耐久性を上げるために、刃先にDLC(ダイヤモンドライクカーボン)がコーティングされているものがあります。
DLCは文字通りダイヤモンドのようなカーボンで、硬くて耐久性がよくて、表面がとても滑らかで潤滑性があります。ひげ剃りの刃は、ステンレス製で刃自体の切れ味はかなり鋭いので、そのままだと肌まで削ってしまいます。そこで刃先にDLCをコーティングすることで、深剃りしても肌にはやさしいひげ剃りができるんですって。
しかもDLCは金属ではないため、金属アレルギーのある人でも使用できるという特徴もあります。このDLCの成膜方法は、イオンプレーティング、スパッタリング、CVD法など、さまざまで、用途に応じて使い分けされています。
用語解説熱処理金属、半導体、セラミックスなどに必要な性質を与えるために、固体の状態で行う加熱と冷却の総称。基本的には焼き入れと焼きなましの2種類に分類される。
アルバックホームページ