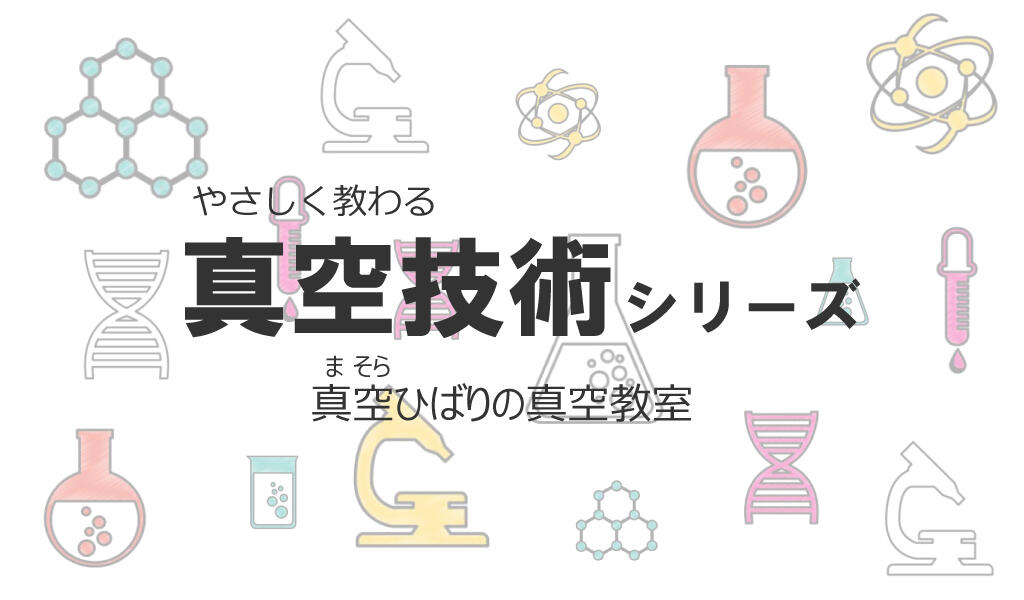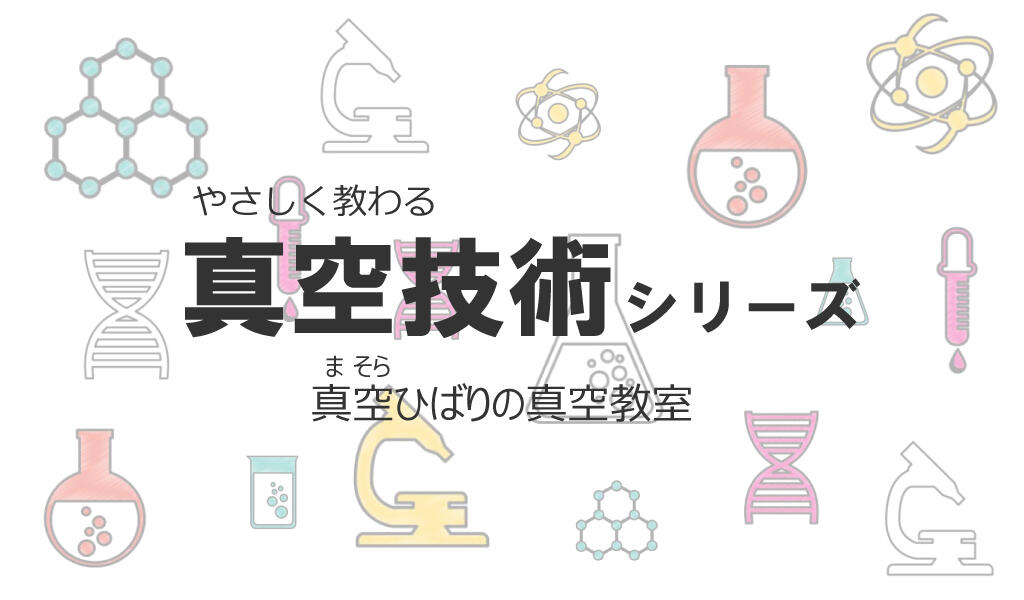
真空ひばりの真空教室 Vol.6
はじめまして! 真空(まそら)ひばりです。この教室で皆さんに「真空」のことをいろいろレクチャーしていきます。よろしくネ♪
気体分子がどれだけまっすぐ飛べるかを表す「平均自由行程」って何だろう?
Vol.5 圧力の差は、空間に存在する気体分子の数「分子密度」でわかるでは分子密度についてのお話をしました。今回は気体中の熱や物質の移動において重要な「平均自由行程」についてお話します。ある閉じられた空間の中には、気体分子が詰まっています。普通の状態では、気体分子はその場にじっとしていることはなくて、熱をもつとあっちこっちへ飛んでいきます。まっすぐ飛んでいったり、隣の分子にぶつかって方向を変えたり、またぶつかって曲がったり、という動きを繰り返します。
こうした動きをする気体分子が、どのくらいの距離をまっすぐ飛べるか、ということを表したものを「平均自由行程」といいます。ただし、実際にはその長さを測るわけではないんです。なぜなら、気体分子は目で見えないから。
そんなわけで、平均自由行程とは、「気体分子運動論」という学問的な取り扱いの中だけでいえる話。理論上の計算値として求められます。簡単に言うと、圧力が低いほど、つまり分子の数が少ないほど気体分子はまっすぐ飛べるので、平均自由行程は長くなるんです。Vol.5で紹介した分子密度は、空間のある部分の数を見ていましたが、平均自由行程はもう少し具体的に、分子の動きそのものを見るため、真空を利用するときにはより現実に近い値として使われます。
真空装置の設計には、平均自由行程の長さを知ることが重要
平均自由行程は、具体的にどのくらいの長さになるんでしょう。通常の大気圧である105Paでの平均自由行程は700Å(オングストローム)=7.0×10-5㎜。短時間の間を考えてみると、分子はほとんど動かず、その場で振動している程度です。これが101Paとなると0.7㎜、10-1Paでは7㎝、10-2Paでは70㎝、10-3Paでは7mとなります。
真空中で物質に膜を付ける蒸着装置などの圧力は、普通10-2Pa~10-3Paを使っています。こうした真空装置の幅や高さはせいぜい1~2mほどで、平均自由行程が70㎝~7mもあれば、るつぼと呼ばれる耐熱性容器を飛び出した分子は、まっすぐ基板に飛んでいくことになります。このように平均自由行程は、実際の真空装置で何を行うかを考えたときに装置自体の設計にもかかわってくる重要な値になるんです。
用語解説
気体分子運動論気体が多数の分子から構成されているという観点に立って、気体の示すいろいろな性質を理解しようとする理論。
圧力と平均自由行程の関係
アルバックホームページ
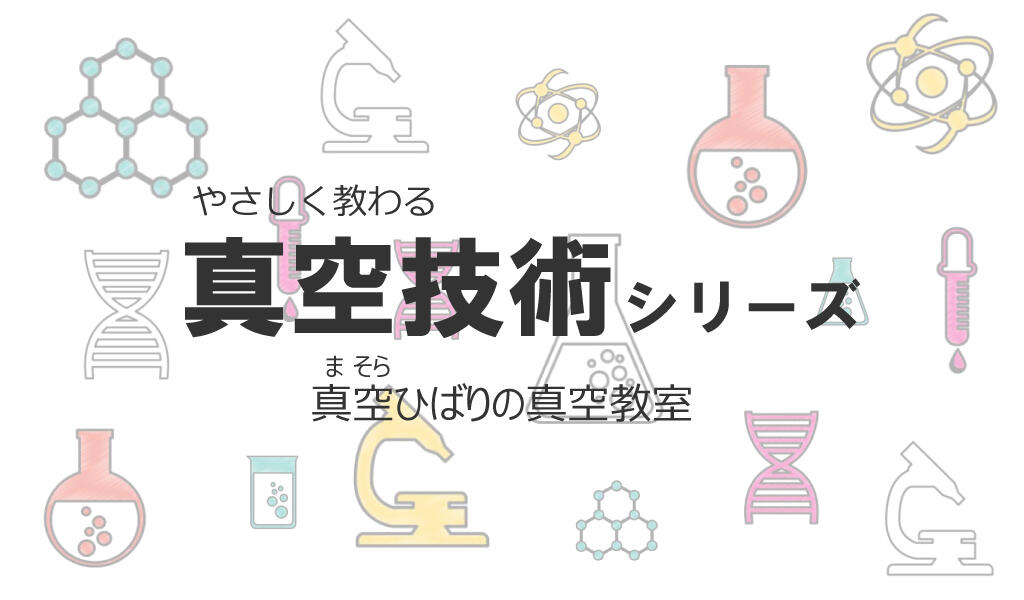
真空ひばりの真空教室 Vol. 5
はじめまして! 真空(まそら)ひばりです。この教室で皆さんに「真空」のことをいろいろレクチャーしていきます。よろしくネ♪
圧力の差は、空間に存在する気体分子の数「分子密度」でわかる
真空の単位って圧力を表す「Pa」が使われているお話を前回しましたが憶えてますか?Vol.4「低真空」から 「極高真空」まで 真空の5つの分類
実際の真空は、こうした圧力からみた場合、かなり低いものになります。
Vol.4でお話した5段階の中の「高真空」に分類される10-3Paと10-5Paでは、力としての違いはほとんどないんです。
なので、圧力としての真空をとらえようとすると無理があって、実際には別のものさしを使って、圧力を置き換えてあげる必要が発生するんですね。それが「分子密度」という考え方なのです。
真空は、閉じた空間の中で大気圧より低い状態のことを言いますが、そこには気体があるので、その分子が一定の体積の中にどのくらいあるかということを分子密度で表すことになります。
この分子密度を利用することで、大気圧に比べて1,000分の1、または10,000分の1というように、測りづらかった圧力の差を、大きな差として認識することができるようになるんです。
差の少ない圧力を差の多い分子数で見る
分子の数で真空を測ると言いましたね!でも、実際に分子の数を数えるということではないんです。そこで、分子密度の計算には、昔から知られている「アボガドロ定数」という定数を利用します。
例えば鉛筆の数を12本で1ダース、12ダースで1グロスと数えるように、化学では分子や原子の物質量を「mol(モル)」という単位で表します。「アボガドロ定数」とは、物質量1molとそれを構成する分子・原子の個数との対応を示す比例定数のことです。
たとえば、空気22.4ℓの中には、6.02×1023の分子が存在することがわかっています。また、大気圧は105Paですから、これによってある圧力下では、どのくらいの分子が存在しているかが求められるんです。
このように分子密度という切り口で真空を見ると、圧力が低い場合に分子の数が少ないということが感覚的にわかってくるんです。なので、力としての差がわかりにくい圧力の世界では、分子の数で見ることで、とても大きな差があることがわかってきます。
真空を利用してさまざまな材料を加工する場合、その表面は常にキレイな状態でなければなりません。そのためになるべく低い圧力にして気体の分子の数を減らしてあげることが重要です。そのときに利用する考え方が「分子密度」だったり、これからの教室でご紹介する「単分子層形成時間」や「平均自由工程」なんです。
用語解説
アボガドロの法則温度、圧力、体積の等しい気体は、種類によらず同数の分子を含むという法則。気体反応の法則を説明するため、1811年にイタリア出身の化学者アメデオ・アボガドロが仮設として提唱した。
アルバックホームページ
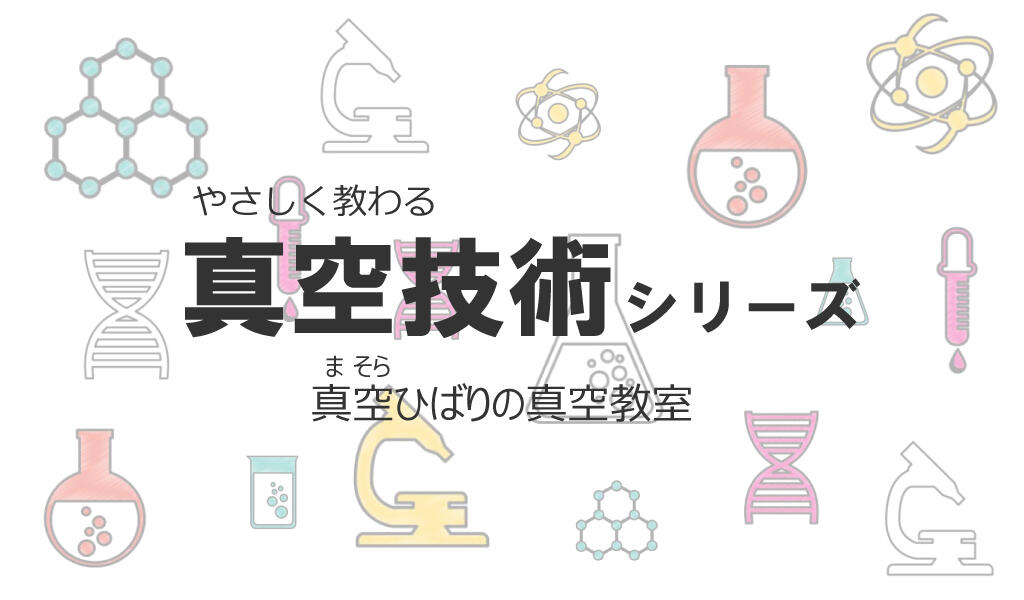
真空ひばりの真空教室 Vol. 3
はじめまして! 真空(まそら)ひばりです。この教室で皆さんに「真空」のことをいろいろレクチャーしていきます。よろしくネ♪
真空を表す単位の圧力は、移り変わってきた
Vol.2では、「空間から気体分子を吸い出すことで真空をつくることができる」というお話をしました。真空とは空っぽの状態ではなく、存在する気体分子の量によることも何となくわかりましたか?
そこで、今回は真空を表す単位のお話です。真空の程度は真空度と言いますが、「圧力」という物理的な量で表すようになっているんです。
圧力とは、単位面積あたりに加わる力のことで、国際(SI)単位では、1平方メートル(㎡)の面積につき1ニュートン(N)の「N/㎡」や、「 Pa(パスカル)」が使われています。
圧力の単位が使われ始めたのは17世紀頃。イタリアの物理学者でガリレオの弟子のトリチェリによる水銀柱を使った実験から、水銀柱の底面にかかる圧力を基準にした、「mmHg(ミリメートルエイチジー、または水銀柱ミリメートル)」が使われていました。圧力を測定する圧力計が水銀柱を用いていたことに関連してなのか、この水銀柱をもとにした単位が長い間使用されていたんです。
圧力を表す単位はmmHg→Torr→Paへ1960年代になると「mmHg」に替わって「Torr(トル)」が使われるようになりました。水銀柱の実験をしたトリチェリにちなんでつけられた単位です。mmHgとTorrは、厳密には定義が異なるため1/7,000,000だけ数字が異なりますが、実用的には1mmHgと1Torrは同じとして使っても問題はなかったようです。
ところが、ずっと長く使われてきたmmHgは新計量法の施行により1993年から、商取引に使用してはいけない単位に分類されてしまいました。そのため文書や論文では「国際(SI)単位」の「Pa」を使用することが奨励され、実際にPaで圧力を表すことが多くなっています。
Paは、低地と山頂で水銀柱の高さが異なることを示したフランスの数学・物理学者、パスカルにちなんで名づけられた単位です。ちなみにパスカルといえば、「密封された容器の中の静止流体の1点に圧力が加わるとどの地点でも圧力は等しくなる」という「パスカルの原理」をはじめ、気体や圧力の法則に関する業績をあげた人ですね。
日本では天気予報で、気圧を表記するときに、以前は「mbar(ミリバール)」を使っていましたが、現在では「hPa(ヘクトパスカル、1hPa=100Pa)」を使っているの、知ってた?
Barはセンチメートル・グラム・秒を基本としたCGS単位系のdyne/c㎡の圧力単位で106dyne/ c㎡=1barとなります。今回は、「真空」は「圧力」の量で程度を表すということ、その「単位が時代とともに移り変わってきた」ということについてレクチャーしてみました。
用語解説
水銀柱
気圧とつりあう水銀柱の高さを測定することによって、水銀柱の圧力、すなわち気圧を算出することができる。
パスカルの原理
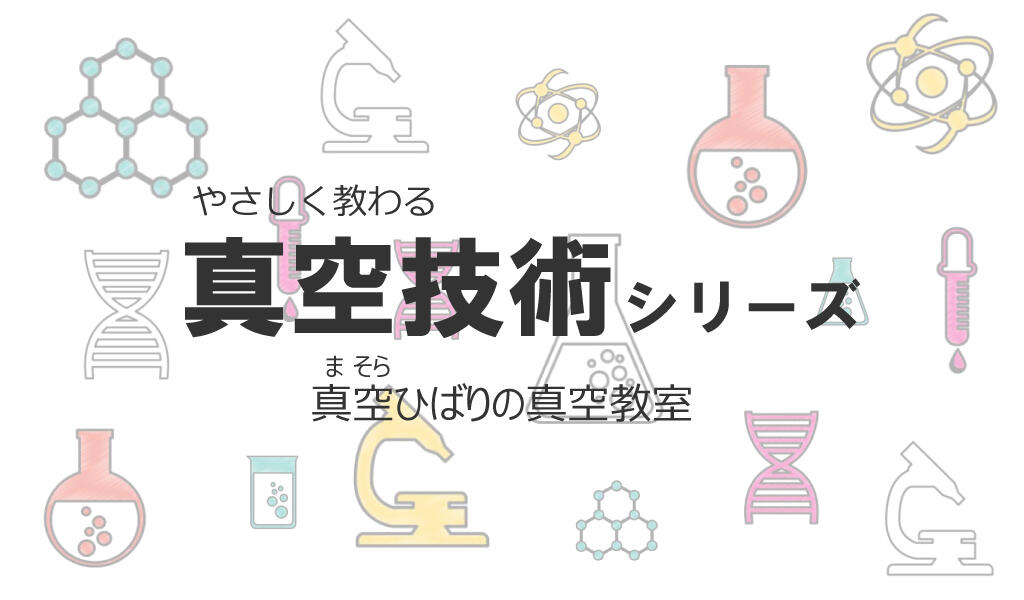
真空ひばりの真空教室 Vol. 2
はじめまして! 真空(まそら)ひばりです。この教室で皆さんに「真空」のことをいろいろレクチャーしていきます。よろしくネ♪
空間から気体分子を吸い出すことで「真空」をつくることができる!?
Vol.1では、真空について「空間に何もない状態ではない」「人が真空ポンプを使って作り出した低圧状態である」というお話をしましたが、では、「空気は何でできているのか」知っていますか?
空気の中に一番たくさん含まれているのが、窒素と呼ばれるガスで約78%。 次が酸素で約21%。もちろん酸素は、私たち人間をはじめ、生き物が生きていくために大切なものですね。その他には約0.93%のアルゴンなどで構成されています。
また、量は多くありませんが水蒸気や二酸化炭素、自動車の排気ガス、あるいは私たちが匂いとして感じる有機化合物など実際の空気にはとてもたくさんの物質が混ざっています。私たちの周りにある気体は、このような物質のとても小さな分子が、高速でさまざまな方向へ動き回っている状態としてイメージすることができます。私たちはそれらのたくさんの分子の集まりを空気として感じているんです。
空気中の気体分子を真空ポンプなどで吸い上げてあげることで、容器の中の気体分子の個数が少ない状態、つまり真空を人工的に作り出すことができるんです。
ちなみに、このことをもとに科学的に気体の性質を議論する学問を「気体分子運動論」といいます。
そして分子の数がとても多い場合、分子全体を統計的に観察することが可能になります。これは「統計力学」として知られ、気体が関係するさまざまな現象が説明できます。
大気圧に逆らって「真空」をつくることは困難
私たちは、昔から気体について、このような現象や知識を理解していたわけではありません。
大気の押す力、「圧力」は意外に大きく、1㎡の平面に約10t(10,000kg)、ダンプカーの積載量分くらいの力がかかります。
この大気圧に逆らって真空状態をつくって維持するのは大変なことです。真空を作り出す方法や道具がなかった頃は、アリストテレスが「自然は真空を嫌う」と考えたのも当然かもしれませんね。
技術が進んだ現在でも、気体分子がまったくない状態をつくることは、とても難しいことなんです。
用語解説
気圧
気圧とは大気の圧力のこと。単位面積の上に大気の上限まで鉛直にのびた気柱の重さに等しくなる。そのため地表より高い所にいくほど、上部の気柱が短くなるので気圧は低くなる。
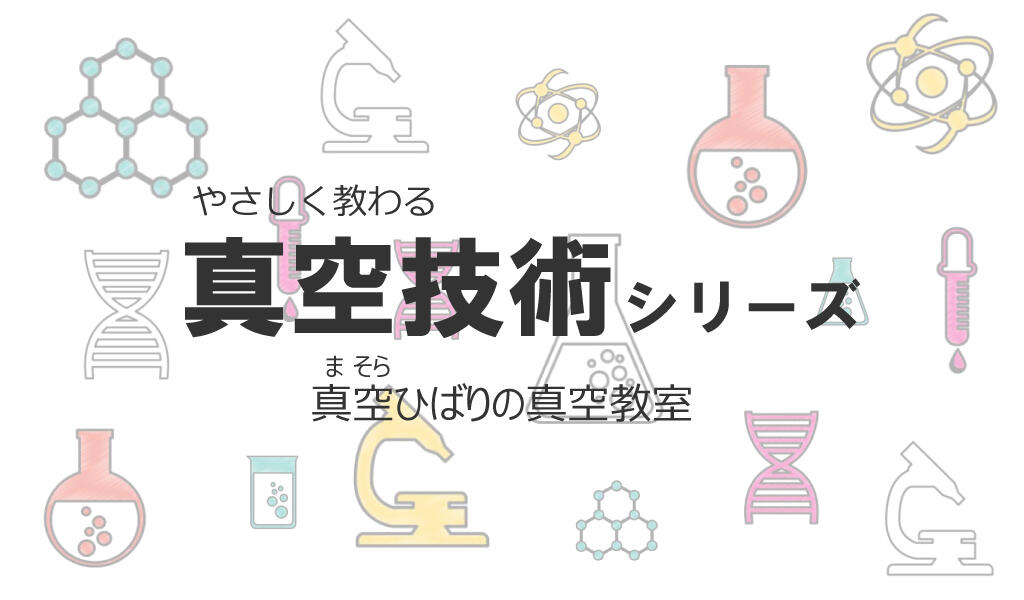
真空ひばりの真空教室 Vol.1
はじめまして! 真空(まそら)ひばりです。この教室で皆さんに「真空」のことをいろいろレクチャーしていきます。よろしくネ♪
空間に何もない状態が「真空」ではないって、知ってた?
真空は、どのような状態をいうのかわかりますか?辞書では、「空気などの物質がまったくない空間」「何もない状態」っていうことになっていますが、では「まったく何もない空間」とはどのようなものなのでしょうか?
真空という概念は、意外に古くからあるんです。古代ギリシャのデモクリトスという名前の自然哲学者は、「原子(アトモス)」が真空という空虚な宇宙空間の中を運動していて、目に見えないくらい小さなさまざまな形と大きさをもったアトモスの運動の仕方で、いろいろな現象を説明できると唱えています。
これに対して、もう一人の哲学者、アリストテレスは、「自然は真空を嫌う」という「真空嫌悪説」を唱え、デモクリトスの考えに反対したことは有名な話です。知ってた?
「真にまったく何もない空間」を理解することの難しさは、昔も今も変わらないということかも知れませんね。
ところで、真空技術における真空とは、このように難しい話ではないんです。日本工業規格(JIS)では、「真空とは、通常の大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間内の状態で、圧力そのものではない」と定義しています。
感覚的に理解しやすい「減圧」や「低圧」という言葉を使うと、「大気より減圧された低圧状態が真空である」と定義することもできます。つまり、真空技術における真空とは、まったく何もない状態ではなく、「大気中の物質がある程度残留している低圧状態のことをいう」ということになります。
でも、そうなると混乱すると思うので、少しだけわかりやすく説明します。例えばエベレストなどの高山になると高いところではかなり空気が薄く、気圧は地表の3分の1しかない低圧状態にあるわけですが、普通は真空状態にあるとはいいませんよね。これはJISでいう「特定の空間」ではないからで、「真空」=「低圧」ではないんです。「真空」と「技術」が組み合わさった「真空技術」では、人が真空ポンプを使って作り出した低圧状態を「真空」であると考えることにしているんです。
だから、「真空とは空間に何もない状態ではない」ということ、わかりましたか?
用語解説
日本工業規格(JIS)
1949年に制定・施行された工業標準化法に基づいて、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣、国土交通大臣など主務大臣が定める国家規格。