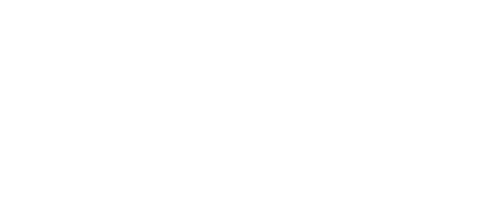This post is also available in: 英語
MEMS開発を通して、人材育成により未来の成果を
現代科学の進歩はエジソンの時代と異なり、多くの場合、一人の力だけで成し遂げられるものではなくなってきている。しかも、多目的・高機能であるために、複合的に絡み合う学問領域が必要とされ、一刻も早い成果が求められる。ますます応用分野が拡大するMEMS(Micro‥Electro‥Mechanical‥Systems)開発においても同様で、東京大学准教授の三田吉郎氏は、MEMSの研究開発はもちろんのこと、次世代の人材育成から産官学プロジェクトのマネージングまで幅広く手がけられている。そこで今回の「視点」は、将来的にも大いなる可能性を有するMEMSを、より高度に発展させるための人材育成法や研究者としての資質・ポリシーなどを交えて三田准教授に語っていただいた。
東京大学 准教授 大学院工学系研究科 電気系工学専攻
大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC)協力教員
ナノテクノロジー・プラットフォーム微細加工東大マネージャー 工学博士
三田 吉郎 氏
(※この記事は、2014年4月発行の 広報誌No.64に掲載されたもので、内容は取材時のものです。)
はじめに:MEMSのはじまりと技術の進展
一般的にMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)とは、ミクロン(1,000分の1mm)スケールの非常に小さな機械のことで、日本語に直訳すると「微小電気機械システム」となる。また、MEMSのことを「マイクロメカトロニクス」あるいは「マイクロマシン」ともいう。
MEMSの大いなる可能性を最初に提唱したのは、1959年に米国カリフォルニア工科大学の教授だったリチャード・P・ファインマン(1965年に朝永振一郎らとともに量子電気磁気学の発展に寄与したとしてノーベル賞物理学賞を受賞)によって、同大学で行われた「There’s plenty of room at the bottom」と称された講演でのことであった。その内容は、10項目に及ぶナノスケールの極微小世界の可能性を中心としたものであった。 エピソードとして次のような話が伝えられている。ファインマンは、1インチの64分の1の直径(約4mm)で動くマイクロモーターをつくった人に、「1,000ドルの賞金を出す」と宣言した。それは、ある技師によって講演の翌年(1960年)にあっさり実現され、ファインマンは賞金を支払ったという。
これにより未踏領域とも言えるMEMSという新たな分野が切り拓かれたのは間違いのない事実であろう。その後70年代、80年代は、半導体圧力センサーや可動ミラーアレイなど、応用分野を広げながら、MEMSはさまざまな形で進展した。
前述のファインマンが賞金を出したマイクロモーターについては、1989年、当時米国カリフォルニア大学のY・タイによって金属やシリコン薄膜を用いたマイクロモーターを、ほぼ同時期の1987年に日本では、東京大学生産技術研究所の藤田博之教授のグループが静電型の転がりモーター、次いで91年にニッケルメッキ構造の静電マイクロモーターを開発した。薄膜堆積、パターン形成(フォトリソグラフィー)、エッチングという半導体プロセスが用いられ、この技法は現在も主流になっている。藤田教授は現在も日本のMEMS研究の第一人者として活躍中である。藤田教授の指導を仰ぎ、強い影響を受けたのが、今回登場いただく三田吉郎准教授であった。
深掘りエッチング技術など、MEMSの三次元構造に貢献
三田:藤田博之先生は私にとってMEMSにおけるかけがえのない恩師です。
鳳紘一郎研究室(鳳-テブナンの定理の鳳秀太郎先生の孫)でMOSFETのパラメータ抽出法の卒業研究を行った後、修士、博士では藤田先生の指導を受け、回路を集積した知能化マイクロマシン(Smart MEMS)の研究を行いました。そのときの成果としては、マイクロマシンとセンサー、マイクロプロセッサとの融合技術を核に、応用として「自己整合的に位置合わせのできる、シリコンシャドウマスク直接微細パターニング技術」、「3次元マイクロ光集積化システム」を実現しました。
MEMSの技術は常に進歩しており、初期の頃は薄膜を二次元的構造に加工するサーフェイスマイクロマシニングが主流でしたが、現在では、ICP-RIE(プラズマ反応性イオンエッチング)によるシリコン深掘りエッチングやウェーハ接合プロセス技術が進歩し、高度で複雑な三次元的な構造が可能となったのが大きな特長です。これがMEMSの進展に大きく貢献しています。深掘りエッチングなどの微細加工は私の専門分野でもあります。
大学院で研究室が変わり、ギャップに苦しみました。簡単な気付きで始めた卒論の成果が国際会議に口頭発表で採択され、天狗になっていた時期で、電子工作も昔から好きだったので、手先の器用さには自信があったのですが、いざ自分でマイクロマシンをつくってみると、同じ装置を使って同じ手順でプロセスをしているはずなのに、先輩が作る物は一発でうまくできて、自分がやるとうまくいかない。毎日「どうしてだろう?」と悩みました。 自分の思った通りにプロセスを組め、
それが一発で成功するようになったのは、ドクター2年生の終わり頃ですね。そのときの経験から、学生には「本当に思い通りになるまでは、軽く4年はかかるから、じっくりやろう(だから、ドクターにまで行こうね)」と言っています。
MEMSの未来技術につながるアメンボロボット開発
MEMSは、自動車、光学機器、通信機器、その各種製造機器など、実に広範な分野に組み込まれているセンサーやプリンタヘッド、ジャイロスコープ、プロジェクタなどに代表される小型で高性能な電子デバイス製造に不可欠な技術である。現在ではさらに高集積化・複合化による多機能な電子デバイス開発に応用されている。将来的には、ナノとバイオの複合技術の確立が課題とされ、その市場規模も2010年の統計では約71億米ドル、2015年には113億米ドルが予想されている。

三田:私は夢のような「ト(オ)イプロブレム(Toy Problem)」の一つとして、ユニークな面ではアメンボロボットの開発に取り組んでいます。「Toy」でも結構そしてできる限り“遠い”方がいい。
2007年5月に英国エジンバラ大学に留学した際、そこで始めたのが水上を自律自走する小型の電子素子、平たく言えばアメンボロボットの研究でした。 自然界の生物にヒントを得た、このような試みは幾多の研究者がそれぞれの得意分野の技術を駆使して手がけていましたが、センチメートル以下の大きさで自走して泳ぐ素子は世界初だろうと思っていました。調べてみると、世界各地に研究者が見つかり、彼らも我々と同じような点で苦労していることがわかり、安心したりライバル心を感じたりです。
誰も手がけていない未踏領域に挑戦することは、研究者の永遠の使命です。私は夢みたいなアプリケーションから研究に入ることをスタイルにしています。世界初となる新しい試みには、さまざまな技術課題が立ちはだかり、それを克服するためには、相当真面目なエンジニアリングが必要となるわけです。そこに浮かび上がってくる技術課題をよく見てみると、いますぐにでもいろいろな分野で利用できる高度な技術でもあるのです。これを私は、「大学発21世紀型のリニアモデル(図1)」と呼んでいます。
将来のMEMS開発には人材育成は不可欠
MEMSは、今後さまざまな産業に適用分野を広げて行くことになる。その研究開発にあたっては複数の学術領域にまたがることになるため、大学が果たす余地が多く残されている分野でもある。一方、そのための人材育成についても大学が重要な役割を担うことになる。
三田:私の場合も研究者としての道が一つありますが、他方、特に本郷キャンパスの教員のミッションとしての教育者の道、人材育成にも力を入れています。つまり、私の左手が研究だとすると、右手は教育者です。実はもう一つ、文部科学省ナノテクノロジー・プラットフォーム事業の東大微細加工拠点を担当しており、まさに「足で」プラットフォームのマネージメントに関わっています。両手両足が常に塞がっている状態で、せめて頭だけは自由になるよう心がけたいと思っています(笑)。
教育者であるからには、万人が理解できるかたちで指導することは大切なことです。私の場合は、手作りの学習教材を授業に持ち込んで電子情報機器学の講義を行っています。その教材を使って学生の目の前で実験してみせる。これが学生には評判が良いようで、今年、第一回の「東京大学工学部ベストティーチング・アワード」をいただきました。

学生には、「遠いプロブレムで良いから、一通り自分で手がけて、経験してみなさい。何かあったら先生がフォローしてあげるから、恐くないよ」と言いつつ、実は背中を押している状態が、私の研究室のポリシーです。 私がフランスに留学して体験した最大の違いは、彼らは、間違いなくデカルト主義の末裔であります。他人の言うことはとりあえず疑う、信じない。自分の中で信じられるものだけを最低限残して、それを組み合わせて論理をつくる。
その割り切りはすごい。割り切るので、専門家が育ちますが、自分の縄張りのことしか相手にしない。たしかに分業といえば分業で、ラグビーのポジションに似ています。日本人であるわれわれは剣道の団体戦のようなもの。つまり、団体戦なのに、一人ひとりが順番にフルに力を出し切って戦う。これが日本流。
私の研究室のポリシーは、ヨーロッパ流と日本流の良いとこ採りです。すべてのポジションを守れるエースも育て、同時に自分のポジションの専門家も育てる。それが理想です。
そのためのステップは、答えを教えてはいけない。高校生までは「頑張って辿り着いてごらん」という指導方法、大学では、「頑張って飛んでごらん」、先生の頭の中にないことを見つけ出すことで能力を引き出します。メソッドというのは、その方法を使えば同じものが誰でもできることであって、独自のメソッドを見つけて自分のモノにすることが重要なのです。
継続は力なり」、MEMSにおいても「失敗は成功の母」
日本のMEMS先駆者の一人である藤田博之教授は、MEMSの本質を3つの“M”で言い表せるという。Micro(マイクロ化)、Mass Production(大量生産性)、Multi Function(複合機能)がそれである。
その概念を持ってすれば、MEMSデバイスは、1ナノから10ミクロンまでの寸法領域でMEMS産業が幅広く発展することになる。さらに、ナノという単位になれば、遺伝子操作のように原子・分子を組み上げて、医療や人体、脳などの医療・バイオ分野にまで、MEMSの可能性は無限に広がっていく。

三田:今後、MEMS研究のための学問領域は広がっていくばかりです。一人の能力はちっぽけなもの。東大の武田先端知では「千人の一歩」をスローガンにしています。つまり、千人の研究者の全員がほんの一歩進むだけで、全体で千歩を進ませることと同じことになる。現在、武田先端知クリーンルームのユーザーは500名ですから、ちょうど道半ばです。
これを実現するためには、学内はもちろん、これまで以上に企業の人たちとの関係を密にしていきたいと思います。企業の人たちにもう一回、大学にリフレッシュにきてもらって、そこで得たものを持ち帰って、新しいビジネスのコアにしてもらいたいですね。大学の研究関連施設は大入り満員。いつも人がいて、技術進歩が絶えない、そういうのを大学発で続けたいと思います。
右に掲載の本は、フランス人なら誰でも知っている『Les Shadoks』というアニメです。愚直な主人公シャドック君は、成功する確率が100万分の1しかないものに対して、本当に100万回実験する。99万9,999回は失敗でも最後の100万回目で成功すると考えるわけです。漫画ではこれを愚かだと笑いの種にするのですが、私はここにこそ本質があると考えます。「継続は力なり」。たくさん失敗すると、たくさん成功するチャンスが増えるという考え方です。漫然と失敗を繰り返していてはだめで、反省することで新しい道が見つかる。MEMS研究においても同じことで、まさに「失敗は成功の母」と言えるでしょう。 私は、アメンボロボットを通して集積化MEMSを実現しようと思っていますが、独り占めせずに、みんなで進むのがいいですね。今までの枠を越えて「モア・ザン・ムーア」(機能の多様化による電子デバイスの進化)を実現するには、いろいろな技術を融合して、日本発、新しい技術を多くの異分野の研究者が集まって一緒に創出することです。
三田 吉郎(みた よしお)准教授のプロフィール
1972年広島県呉市生まれ。1995年東京大学工学部電子工学科卒、1997年同大学修士課程修了、2000年同大学博士課程修了、博士(工学)を取得。1997年9月〜1998年9月、CNRS(フランス科学技術庁)の準研究員として、電子マイクロ電子研究所(IEMN/ISEN)に留学、留学中の成果「マイクロマシンとの集積化に適したフィードバック制御型自律分散プロセッサ」で、2000年2月丹羽記念賞受賞。2000年4月-大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC)助手、VDECが管理する公開装置の効率的サポートシステムを開発し、軌道に乗せる。2001年4月工学系研究科電気工学専攻講師、知的VLSIとの集積を目指したマイクロシステムの研究、自己整合的尖塔加工技術や、ナノ稜線加工技術、自己整合的菱形マイクロミラー作製技術など、マイクロ加工技術に関する研究に従事。
2005年4月工学系研究科電気工学専攻助教授、続いて准教授、武田先端知ビルを核に、ナノ加工技術、LSIとの集積技術から応用システムまでの幅広い分野を開拓中。
(※この記事は、2014年4月発行の 広報誌No.64に掲載されたもので、内容は取材時のものです。)