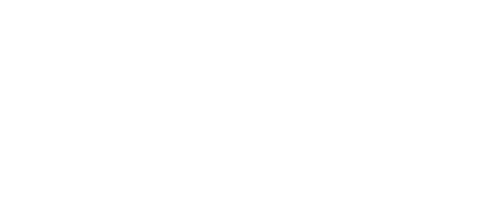This post is also available in: 英語
第二のジャンプはロボット向け「E-ski n」開発
――その後の展開は?
染谷:ベル研究所では、イモ判みたいなスタンプ方式でプラスチックフィルム上に有機トランジスタの電子回路をつくる研究を手がけました。ちょうどその留学中に、ベル研究所の研究者が世界初の電子ペーパーの試作品を開発しました。大変な話題になりましたが、当時このような曲がるエレクトロニクスの研究というのは、すべて表示デバイス向けの研究だったのです。しかし、これは私にとって新しい分野に挑戦する大きな転換期になりました。
日本に戻ってからは、東大生産技術研究所の桜井貴康先生と有機トランジスタの共同研究を始めました。桜井先生はシリコンの集積回路設計では日本を代表する研究者です。
桜井先生は民間企業の経験もお持ちで、シリコンの低消費電力化や回路設計の低コスト化の第一人者でした。当時、印刷で回路をつくると安いと言われていたのですが、印刷でつくるから安いわけでもないという本質を早くから見抜いておられました。そして、印刷でつくると何がいいのかという理由をずっと議論してきました。
シリコンは微細化して限られた狭い面積にたくさんトランジスタをつくることができるので、1個当たりのトランジスタのコストは安いのですが、大きいところにまばらにつくることは得意ではありません。大きい面積に回路をつくる領域においては、印刷に分がある。それをフィルム上に展開すれば、シリコンでは不得手な大面積で、曲がるセンサーが可能になるのではないかと思い、その開発を始めることにしました。
そして、2003 ~ 2004年にわたってロボットの表面に張り付けて、人間の皮膚の感覚に近い「E-skin」のプロトタイプを開発しました。これは2005年に『Time』誌に取り上げられ、表紙にも紹介されました。
ここが第二のジャンプでした。そして今ではさらに進化を遂げ、ロボットだけでなく、人の皮膚に貼り付けたセンサーも開発しています。
失敗の中に次への研究ステップが潜む
――研究者としての理念とは?
染谷:いつも心がけていることは、「自分も楽しく、他人も楽しく」ということです。研究とは、人ができていないことをやることです。当然、
失敗することのほうが多い。なので、失敗してもあきらめずに、しつこくやり続けることが研究者にとって非常に重要な素質です。
研究中うまくいかないと落ち込むわけです。ところが、うまくいっていないことに次へのステップのヒントがある。失敗しても、失敗から学んで、挑戦し続ける。このプロセスは、ともすると苦しくなりがちですが、自分が面白いと感じることなら没頭できますし、プロセスを楽しめます。楽しいことは、続けられます。
それがいかに面白いかを自分で納得できれば、新しいものを生みだそうとする喜び、生きがいに感じる研究者魂が掘り起こされます。そして、寝食を忘れて研究に没頭していく。研究は、そういうみずみずしい感性と情熱がないとできないことなのです。まさに「面白い」というキュリオシティ(好奇心)が大学における研究活動の原動力なのです。企業においては事業としての収益性が求められますが、大学の場合には、本人の興味、キュリオシティが原点です。ですから大学の研究は、市場や事業だけを考えていたら思いつかないようなことに気がつくこともあるわけです。企業側から見
ると、そのような大学の研究成果を